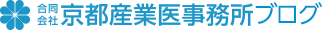日経ビジネス人文庫より発刊されている『模倣の経営学』(井上竜彦著)を読んでおります。
井上氏の書籍は、『ブラックスワンの経営学 通説をくつがえした世界最優秀ケーススタディ』に続き2冊目になります。
さてこの『模倣の経営学』の主題は「トヨタもセブンイレブンもスターバックスも、優れた企業は「真似て、超える」ことで成功した」という内容を整理して発展させた内容です。
真似るという行為は、「猿真似」という言葉があるように、良い印象がありませんが大事なことです。
本著で初めて知ったのですが、世界の製造業に偉大な影響を与えているトヨタのジャスト・イン・タイムのシステム、生みの親の大野耐一氏はスーパーマーケットの仕組みを人づてに聞いたことから発展させたそうです。
真似るという行為は本当は素晴らしいです(ここでいう真似るとは陳腐なコピー商品や、版権・パテント等無視した盗作まがいのものではありません)。
「真似ぶ」は「学ぶ」と近い言葉だと以前聞いたことがあります。
アイザック・ニュートンは「私がかなたを見渡せたのだとしたら、それはひとえに巨人の肩の上に乗っていたからです。」という言葉を残しています。
『模倣の経営学』にもありますが、「守破離」という言葉もあります。
「守」とは師から教わった型を「守る」こと
「破」とは自分にあったより良い型を目指し、教わった型を「破る」こと
「離」とは自分自身が造り出した型の上に立脚した個人は、最終的には型からも自在に「離れ」進化すること
注目すべきなのはまず最初に「守」が来ることです。
ただ、「守」に入るためには、まず良い師を見つけないといけませんね。
では、そもそも良い「師」とは何でしょうか。そしてどうすれば見つかるのでしょうか。
これは、簡単な問いではなく私もまだ見つけていないので、今後進捗あればここに書こうと思います。
ただ、今言えることは「師」は探すと見つからない、今目の前にあることに真剣に取り組んでいく中で、ぼんやりと目の前に輪郭を持って現れる存在なのではないかということです。
簡単に言うと、「足元の地面を一生懸命掘り続けていたら、少しずつ地面の中から出て来た」といったところでしょうか。どこか探検して見つけに行くのではないです。
私は、幸いなことにこれまで超がつくほど一流の方ばかりを師という形で出会ってきました。
世界有数の海外の巨大企業でリーダー育成のエリートコースを切り抜けてきたような方から、アメリカに身一つで渡り一大事業を築き上げた方、独学でデータ解析から熱伝導・対流の制御に関する特許等を抑える等一人でやってしまうような方まで、普通に考えてどうしたら会えるのかわからないような方ばかりでした。
これらの方々、会いに行ったわけではなく、目の前の問題に真剣に取り組んでいるときに、突然思いがけぬ形で紹介があったり、就職した先のベンチャー企業の上司だったりという形でした。
出会いとは不思議なものです。私は、人との良縁は自分で探すのではなく、必死に手足をバタバタして浮き上がろうと努力している中で、いつの間にか指に引っかかっている糸のようなものと考えています。
『模倣の経営学』からだいぶ脱線してしまいましたが、この本を読んでいるうちにこのようなことを思いました。
井上氏の書籍、学術的な最新の情報等も盛り込んでいるため読み応え抜群で勉強になるのでお勧めです。
P.S.
『ブラックスワン』といえば映画がありましたね。私は、映画の内容を知らずに映画館に観に行き、この世の終わりぐらいに怖かったです。
人間心理を扱った映画の方が、単純なホラーより後味は最悪ですね(笑)。
社会性、芸術性は非常に高く素晴らしいのですが、個人的には苦手でした。
コアなファンはできそうな独特の映画でした。
橋本圭司