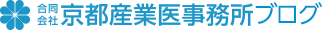この小さな子犬は、生後2ヶ月にもならないうちに、母親から引き離されて、ペットショップのショーケースの中で震えていました。
何故そんな、残酷なことができるのでしょうか。
ただただ、この子に、善き飼い主が現れ、愛情を受けて幸せな生涯を手に入れてくれますようにと、祈るばかりです。
♡♡♡虹の橋♡♡♡
天国の少し手前に、「虹の橋」と呼ばれる場所があります。
地上にいた頃、愛されていたペットたちは、死ぬとその「虹の橋」へ行くのです。
そこには、草原や丘が広がり、彼らはいっしょになって走ったり遊んだりすることができるのです。
たっぷりの食べ物と水、そして日の光に恵まれ、皆で温かく快適に過ごしています。
病気にかかっていたリ老齢だった子たちは、ここに来て活力を取り戻し、
傷ついたり体が不自由だった子たちも、もとどおりの健康な体を取り戻します。
遠く過ぎ去った夢のように。
彼らは幸せに暮らしているけれど、ひとつだけ満たされない思いがあります。
彼らにとって特別な人、あとに残してきた大切な人と、共にいられないのを寂しく感じているのです。
彼らはいっしょに遊んで時を過ごしていますが、ある日、そのうちの一匹が、ふと足を止めて遠くに目を向けます。
目はきらきらと輝き、体は喜びに溢れて、震えはじめます。
突然、彼は皆から離れて、緑の草地を跳ぶように走り出します。
待ち焦がれていた大切な人を見つけたのです。
やっと再開できた彼らは、抱き合って喜びあいます。
もはや二度と別れることはありません。
互いに愛する友を、優しく撫で続け、信頼にあふれた瞳で見つめ合います。
互いの人生から長い間、姿を消していたけれども、心からは一日たりとも消えたことがないその瞳を。
それから彼らは一緒に「虹の橋」を渡ってゆくのです。
♡♡♡虹の橋のたもとにて♡♡♡
天国の少し手前に、「虹の橋」と呼ばれる場所があります。
「虹の橋」の少し手前には、緑あふれる谷があります。
大切なペットたちは、死ぬとその場所へ行くのです。
そこにはいつも食べ物と水があり、気候は常に暖かい春のようです。
歳をとって、からだが弱っていたものは、ここへ来て若さを取り戻し、
体が不自由になっていたものは、元どおりの姿になります。
そして一日中一緒になって遊んで過ごします。
けれども、橋のそばには、様子の違うものたちもいます。
疲れ果て、飢え、苦しみ、誰にも愛されなかった動物たちです。
他の子たちが一匹、また一匹と、
それぞれが、かつて愛し愛された人と一緒に橋を渡っていくのを、寂しそうに眺めています。
彼らには愛し愛された人などいないのです。
生きている間、そんな人間はだれひとり現れなかった・・・。
しかし、ある日ふと、橋への道の傍らに、誰かが立っているのに気づきます。
彼はそこに繰り広げられている友の再会を、羨ましそうに眺めています。
地上に生ある間、彼はペットと暮らしたことがありませんでした。
彼は疲れ果て、飢え、苦しみ、だれにも愛されなかったのです。
そんな彼がポツンと立っていると
愛されたことがない動物が、どうして一人ぼっちなのだろう、と近づいて来ます。
愛されたことがない動物と、愛されたことがない人間が、互いに近づくにつれ、奇跡が起こります。
なぜなら、彼らは一緒になるべくして生まれたからなのです。
地上では巡り会うことができなかったけれど、特別な人と、大切なパートナーとして。
今、やっと「虹の橋」のたもとで彼らの魂は出会い、痛みや悲しみは消え、友は一緒になれるのです。
そして、いっしょに「虹の橋」をわたり、もう二度と別れることはありません。
(橋本由美)